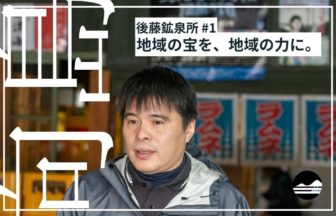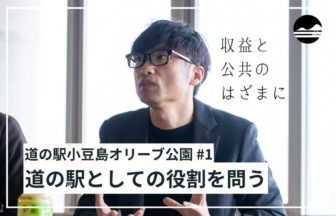「はなれじま広報部」では、広報戦略やECサイトの観点から、離島を振興するための実例やノウハウについてご紹介しています。
今回は、後藤鉱泉所で代表を務める森本さんにお話を伺い、3本立てのインタビュー記事を制作いたしました。#03では、後藤鉱泉所の店舗運営や広報に関する戦略と、目指すビジョンについてお話いただいています。
>>#1「受け継がれた“幻のサイダー”の味を守るために」はこちら
>>#2「低収益のビジネスモデルを覆した、付加価値を生み出すコラボレーション」はこちら
▼後藤鉱泉所 四代目代表 森本 繁郎氏
1977年生まれ、広島県豊田郡大崎上島町出身。2021年3月に竹原市役所を退職し、同年4月に後藤鉱泉所を事業継承する。先代が守ってきたサイダーの味を大切にしつつ、「怪獣レモンサイダー」をはじめとする新商品を続々と開発するなど、次なる担い手にバトンを繋ぐため積極的に試行錯誤をしている。
コンビニの動線を意識!
客単価を向上させる売り場づくり
—— #2では商品開発の観点から客単価を向上させるための施策についてお伺いしました。その他、売り場での取り組みはありますか?
先代の時から一貫していることなのですが、来店されたお客さんとのコミュニケーションを大切にしています。基本的には、商品の特徴やおすすめポイントをひとつひとつ丁寧に説明させていただいています。
ただ、繁忙期など、接客に多くの時間を割くことができない時もあるため、商品の説明を記載したポップを置いて、お買い物を楽しんでいただけるようにしています。中にはパッと見ただけでは魅力が伝わりづらい商品もあるので、分かりやすさを重視したポップ作りに努めています。
—— 商品のポップってつい読んじゃいますよね。一見して特徴を知ることができれば、手に取るきっかけにもなります。
そうですね。また、お客様の導線を意識して、陳列方法にも工夫をしています。たとえば、よく売れる商品は売り場の奥に設置して、そこに至るまでにその他の商品も見てもらえるようにしました。
売り場作りの参考にしたのはコンビニエンスストアです。コの字型に流れるような動線を作り、販売数の多い商品までの距離を長めにとっています。こうすることで、こちらが売りたい商品から人気商品までの流れを自然と作ることができるんです。

店内の商品は導線を意識して配置しているそう
—— たしかに、売り場の入り口付近にはオリジナルグッズの雑貨があって、奥に「怪獣レモンサイダー」などの売れ筋商品が置いてありますね。何気なく商品が並んでいるのかと思いましたが、森本さんの狙いがあったんですね…。
ちょうど取材中にも5人組の観光客が来店。ひとつずつ丁寧に商品の説明をしながら、人気商品の元へと誘導する森本さん。柔らかな口調と丁寧な接客トークに、5人の手は自然と商品へと伸びていきます。続いては、認知拡大の手法についてお伺いします。
「昭和レトロ体験」で付加価値を提供
—— 後藤鉱泉所を広く知ってもらうための取り組みについて教えてください。
後藤鉱泉所の空間をフォトスポットとして演出することで、写真をSNSでシェアしていただけるようにしました。やはり、お客様の口コミやSNSでの投稿は認知向上に絶大な効果をもたらします。まずは「写真を撮りたい」と思っていただけるよう、売り場のレトロ感を演出しました。
—— たしかに、空間全体が昭和の世界観で統一されています。
世界観の演出には心血を注ぎました。先代の頃から受け継がれてきた自然な昭和らしさを引き出しつつ、あえて昭和感を出している部分もあります。
例えば、マルゴサイダーのポスター。Instagramでレトロ調のイラストを書いてる方にお願いして、昭和レトロな一枚を制作してもらいました。店内の雰囲気にマッチしていて、とても気に入っているんです。

店内の世界観に合わせてレトロなポスターを制作
—— 繊細なバランスで「昭和感」が作られていたんですね…。言われないと気づかないものも多いです。ここに来るとタイムスリップしたような気分が味わえますね。
そうなんです。ここではただサイダーを飲んで帰るだけではなく、ぜひ昭和を体験しに来てほしいと思っています。お客さんにとっての「知らなかった」や「初めて」を体験してもらうことで、ここでしか得られないような感覚を味わってほしいんです。
最近では、若い年代の方を中心に栓抜きを使ったことがない方も多くいらっしゃるようなので、あえてご自身で栓を開けていただくようにしました。昔だと当たり前だった何気ない所作ですが、新鮮な体験ができると好評です。

取材陣も栓抜きを体験
そうした影響もあるのか、マルゴサイダーのロゴが入った栓抜きはオリジナルグッズの中で一番人気の商品になりました。サイダーと一緒に購入される方が多いですね。
—— 最近では栓抜きがない家庭も珍しくないので、思い出と一緒にお土産を持ち帰ることができるのは良いですね。

オリジナルの栓抜きがグッズとして販売されている
商品価値をより一層高めるきっかけを
—— 今後挑戦したいことはありますか?
動画を使った情報発信ですね。サイダーが作られていく過程を撮影・編集してTikTokやYouTubeショートで発信できたら、製造過程にも興味を持っていただけるのではないかと思っています。
特に古い機械が現役で稼働している様子にはロマンを感じていただけるはずです。飲料を製造する機械はすべて先代から受け継いだもので、消耗品を交換しながら使い続けてきました。一番古いものは戦前から使われていると聞いています。
特に水と炭酸を合わせる混合機は心臓部と言われていて、マルゴサイダーの味わいに影響を与えるものです。味を受け継ぐためにも長く使い続けているのですが、その光景も非日常な昭和体験だと感じています。そうしたストーリーを伝えることで、商品価値も高めていきたいですね。

特に混合器は使い続けたいと語る森本さん
—— 製造過程を発信することで、商品価値は高まりそうですね。バーチャル工場見学のような発信の仕方も面白そうです!
マネタイズを成功させて、後継者不足の事業を救いたい
—— 今後の展望についてお伺いします。事業の拡大は視野にありますか?
実は、事業規模を際限なく拡大していこうとは考えていないです。まずは収益源を安定させ、後継者問題を解決へと導きたいと思っています。
後藤鉱泉所に限らず、後継者が不足する最大の要因はマネタイズがうまくいっていないからだと私は考えています。生々しい部分ではありますが、すべての事業者が避けては通れない道です。後藤鉱泉所で成功事例を作って、同様の課題を抱える事業者が生き残っていけるような道を開きたいですね。
経営を安定させて昔ながらの味を後世に残せるような地盤ができれば、他の方に事業継承をして、後継者が不足する別の事業者を救いにいくことも視野に入れています。「地域の宝を、地域の力に。」というビジョンは、どの事業者にも当てはまるものだと思います。
—— 事業を継承して、たった2年で売上を約5倍にした森本さん。収益を向上させるためには、成長戦略が必要とされますね。貴重なお話ありがとうございました。
「地域の力を、地域の宝に。」まさにこの一言に尽きる取材内容でした。同じビジョンを持って活動するビジネスパートナーとの出会いは、転機でしたね。これからさらに、向島や尾道が盛り上がることに期待です!
そして、事業継承の思いについて。現在も、日本全国で後継者不足が叫ばれていますが、後継者を見つけること自体がゴールではないですもんね。むしろ、課題は山積みです。地域の灯を消さないために切磋琢磨する森本さんに感銘を受けました。森本さん、ありがとうございました!
>>#1「受け継がれた“幻のサイダー”の味を守るために」はこちら
>>#2「低収益のビジネスモデルを覆した、付加価値を生み出すコラボレーション」はこちら
.png?1715508830)